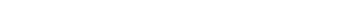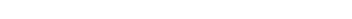- HOME >
- 専門家による技術解説 >
- IoT電源(環境発電・ワイヤレス給電)の動向と種類・特徴
IoT電源(環境発電・ワイヤレス給電)の動向と種類・特徴
2021.05.16
IoT電源(環境発電・ワイヤレス給電)の動向と種類・特徴
1. IoTと電源
IoTあるいはセンサはフィジカルな現実空間とサイバーなコンピュータ上の空間を結ぶインターフェースである。最近は現実の世界をコンピュータ上の双子のように実現するデジタルツインが流行り言葉になっている。センサを多くばらまきネットワークで接続するとのコンセプトはIoTに始まるものではない。スマートダスト、ユビキタスあるいはワイヤレスセンサネットワークなどの言葉で2000年頃から叫ばれてきた。しかし、期待ほどの普及はしていない。普及を阻む最大の要因が電源問題であると言っても過言ではない。
少し前にトリリオンセンサが提唱された。2015年までに1兆個のセンサを世界中に設置する壮大な構想であった。しかし、「3年寿命のバッテリを搭載した1兆個のセンサを取り換えるにはオーストラリアの人口に匹敵する2,300万人の交換要員が必要になる」との試算もあり、最近の予測では2025年に250億個と大幅に下方修正されている。
電源問題を解決する切り札として環境発電に対する期待は高い。周りにある光や振動、熱、電波などの捨てられてきたエネルギーを収穫(ハーベスト)し利用する技術で、エネルギー・ハーベスティングとも呼ばれている。主な環境発電方式とおおよその発電電力を表1にまとめた。発電電力だけでなく、開放電圧が0.01mVのものもあれば80V以上と高いものもあり、しかも安定しない。センサや無線回路を駆動させるには高効率の電圧変換(電源)回路が必要となる。
表1. 主な環境発電方式とおおよその発電電力
| ソース | ソース エネルギー密度 | 概略発電電力 | 開放電圧 | |
|---|---|---|---|---|
| 光 | 野外 | 100mW/cm2 | 10mW/cm2 | DC:0.7V |
| 室内 | 100μW/cm2 | 10μW/cm2 | DC:0.7V | |
| 振動 | 機械 | 1G@50kHz | 800μW/cm3 | AC:80V |
| 人間 | 0.1G@1kHz | 4μW/cm3 | AC:80V | |
| 熱 | 機械 | 100mW/cm2 | 1~10mW/cm2 | DC:0.02~1V |
| 人間 | 20mW/cm2 | 30μW/cm2 | DC:0.02~1V | |
| 電波 | 携帯電話 | 0.3μW/cm2 | 10~100nW/cm2 | RF:0.01mV |
環境発電のコンセプトも「IoT」と同じぐらいの歴史を持っている。原理自身も新しいものではない。しかし、期待ほどの普及は見せていない。標準化も進み比較的普及しているのはEnOceanぐらいである。2001年にSiemensからスピンアウトしたEnOcean社が、EnOceanアライアンスを設立(2008年)し、無線技術も含めた普及・標準化活動を続けており、国内の大手企業も参加している。例えばスイッチを押すエネルギーを電力に替えて、無線で照明を操作するとのコンセプトである。身の回りに存在するエネルギーを使うのとはやや趣を異にする。
環境発電が普及しないのは、エネルギー密度がそもそも低く、必要な電力を発生させようとするとセンサ本体や電池に比べて物理的サイズや大きくなることも原因かもしれない。これを打破するため、強制的に電波(マイクロ波)などエネルギーを供給してエネルギー密度を高めるワイヤレス給電のコンセプトが注目されている。国内では利用できる周波数帯域が2020年に決まり、実用化に向けた一歩を踏み出したと言える。工場内のセンサへの給電などが考えられている。
医療へのIoT技術の適用も活発に行われている。ウェアラブルやスマートテキスタイルのように常時身に着けるセンサもあるが、究極は身体にセンサを埋め込むことである。給電をどうするのかが一つの課題であり、電磁誘導や超音波などのエネルギーで伝送するワイヤレス給電が解決策として各種検討されている。
2. 環境発電
2-1. 光エネルギー
太陽光発電は化石燃料に替わる一大自然エネルギー源として普及が進んでいる。センサにもこの光のエネルギーを使うとの発想はごく自然な発想であり、しかも光電変換デバイスは揃っているように思われる。街角の電柱などに設置し、騒音や大気汚染、温度などを監視するシステムが欧州のスタートアップで製品化されている。
現実はそれほど簡単ではない。野外で使うには、夜や雨天では使えず、さらにはゴミや葉で覆われて発電しなくなる危惧がある。特に後者は電池と同じようなメンテナンスコストを発生させる。
屋内では光のエネルギーが1/1000に落ちてしまう。またセンサの置かれている機械室はさらに暗い。高効率の光電変換デバイスが求められている。色素増倍太陽電池は高効率として知られている。また薄膜の有機太陽電池は柔軟で機械や人体などの曲面にも貼り付けられる特長がある。このような室内光でも十分な電力を発生できる有機系の高効率太陽電池の材料開発は多くの機関で研究開発が進められている。高効率化の追求とともに高信頼化が技術課題である。
2-2. 振動エネルギー
機械は振動する。機械の振動から故障の予兆を検出する技術はIoTの応用の一つとして検討が進められている。電源にもこの振動エネルギーを使えばよいとの発想である。振動を電気に変える仕組みとしていくつかの方式が検討されている。 半永久的な電荷を蓄積する絶縁材料エレクトレットの振動から静電誘導の原理で電力を取り出す方式については、2013年に東京大学を中心に「エレクトレット環境発電アライアンス」が結成され、実用化に向けた検討が進められてきた。MEMS技術と組み合わせることによって小型化が可能になる。
コイルの中に挿入した磁石の振動を用いて発電する電磁誘導方式も古くからある発電方式である。少しかさばるところがこの方式の難点ではある。懐中電灯の充電に使うといった、「災害グッズ」としての用途も検討された。また、電車の振動を利用して発電し、車両監視に使うといったものの開発も行われている。コイルの中に挿入した2本の板状の磁歪材料(平行梁)の振動から電磁誘導で電力を取り出す方式は金沢大学などで研究開発が行われている。鉄とガリウムの合金からなるGalfenolを磁歪材料として使い、シンプルな構造と堅牢性が特徴である。
梁状の圧電の振動から電力を取り出す研究開発も盛んである。PZTでもAlNでも有機圧電薄膜(PVDF)でもよい。例えばステンレス板(カンチレバー)の両面にこれらの圧電材料を堆積させればよい。MEMS技術との相性もよく、小型化も可能である。 振動方式の欠点は効率を上げるために共振を利用しているところである。そのために変換できる振動周波数帯が限定されてしまう。個々の機械などの対象物によって振動周波数は異なり、個々にチューニングが必要になる。非線形振動を用いて振幅を大きくし、変換効率が高めるという研究もある。ただし、大振幅を維持するのは難しく、外乱によって簡単に振幅の小さなモードに遷移してしまう。
また、そもそもモータなどの機械はバランスを崩す恐れのある振動発電の装着を嫌う(正常動作を保証しない)といった制約もある。
2-3. 熱エネルギー
温度差があればゼーベック(熱電)効果で電気に変換することが出来る。冷却に利用されるペルチエ素子を反対に動かせばよい。原理は簡単で、機械は熱を発生し、材料・デバイスも揃っている。比較的早く実用化も進んだ。 問題は放熱である。高温は熱源によるが、温度差を付けるには低温側にフィンなど装着して、大気に対してしっかりと放熱する必要があり、結果として脆弱である程度の大きさになる。
変換効率の改善も課題であった。例えば、豊田工業大学などではCuとSeを掛け合わせて発電効率を大幅に向上させた材料を開発した。また、物質・材料研究機構(NIMS)などでは5℃程度の微小温度差でも85μW/cm2の電力を発電できる新材料(Al2Fe3Si3)を開発した。従来材料であるビスマス・テルル(Bi2Te3)に比べて、希少材料や毒性材料も使用せず、変換効率や機械強度および化学的耐性も強いという。
スピン流熱電変換はスピン流と呼ばれる新しい物性を利用したエネルギー変換技術であり、2008年に最初の報告があり、その後変換効率を上げる材料開発が続けられている。CoPt系の材料で60μW/cm2(温度差10度)まで開発が進んでおり、いずれ1mW/cm2に達すると期待されている。
他の機関でも熱電新材料の研究開発は進められており、熱電発電が再び脚光を浴びる日も遠くないと思われる。
2-4. 電波エネルギー
放送や携帯電話、WiFiなど電波(高周波/マイクロ波)は周波数の隙間なく使われており、昼夜によらず空間に溢れている。これをうまく利用すれば安定した発電が可能になる。マイクロ波を直流に変換するレクテナ(rectenna:rectifying antenna)と呼ばれるアンテナで発電(変換)する。アンテナサイズは周波数に反比例するので、マイクロ波領域では数cm角まで小型化できる。しかも印刷技術を用いてフレキシブルな薄膜上に形成できるので、安価にでき、設置も簡単である。直流に変換する整流素子もデバイスの改良で高効率化が進んでいる。
エネルギー密度が他のソースより小さいので、発電電力は限定的である。低消費電力の無線ICと組み合わせて、パッシブRFセンサタグとしての商品化が始まっている。
光や振動、熱エネルギーを用いた環境発電の普及が進まない中、電波エネルギーを用いた発電は改めて注目されている。電力が限定的なら、マイクロ波を送信すればよいのではないかとのコンセプトが、後に述べるマイクロ波給電の発想であ
2-5. その他エネルギー
尿や樹液を用いた発電が立命館大学で検討されている。尿や樹液を電解質として発電させる原理である。オムツに装着し、失禁センサとしての利用を想定している。また、森林に設置する森林火災用センサとしての利用も考えられる。
土壌に生存する発電菌を利用する発電の研究は物質・材料研究機構(NIMS)などで行われている。土壌状態や温度などを監視するセンサの電源として利用することを想定している。なお、発電菌は海底やヒトの体内にも生存しているようで、広い応用も期待できる。
3. ワイヤレス給電
3-1. マイクロ波給電
マイクロ波を用いた環境発電では発電電力が十分ではない。そこで、マイクロ波を送信し、発電電力を大きくしてセンサを動作させようとする研究開発が盛んになっている。古くから行われてきたマイクロ波給電と環境発電を合体させたコンセプトである。総務省で検討が進められ、2020年には3つの周波数帯(920MHz、2.4GH、および5.7GHz)の使用条件が決められた。
第1ステップは920MHz帯で屋内工場や介護施設等での実用化を考えている。5m程度の伝送距離で数μW~数百μWのセンサへの給電を考えており、人との共存を許している。第2ステップは2.4GHz/5.7GHz帯を使用し、10mの距離で最大2Wの給電まで行うシステムで、有人あるいは無人の屋内工場、プラント、倉庫等でのセンサや表示装置への給電を想定している。ビームフォーミング技術を用い、必要な機器へ集中的に給電する。ヒトが経路に入る場合には給電を止める安全対策もとる。
米国のOssia社などのスタートアップは家庭内電子機器へのマイクロ波給電を実用化しており、米国連邦通信委員会(FCC)の許可を得て販売している。使用周波数は915MHz帯、2.4GHz帯および5.8GHz帯である。Ossia社はマルチパスといった先端無線技術を活用したシステムで、国内企業と提携して車内でのワイヤレス給電の商品化にも取り組んでいる。
共振型のワイヤレス給電や環境発電が伸び悩む中、センサに対する新しい給電形態として今後の展開が楽しみな技術領域である。
3-2. 埋込生体センサ用ワイヤレス給電
生体情報を常時モニタする需要は糖尿病や高血圧などの生活習慣病の監視や術後のケアなどで高まっている。また、ウィズ/アフターコロナで医療のオンライン化が進む中、その普及は加速するものと考えられる。身体内に医療機器を埋め込みモニタすることで、その精度は高まると考えられる。蓄電池は内蔵するものの、その交換は手術を伴うため、身体外からワイヤレス給電することが望ましい。
例えば、米国のスタートアップEndotronix社は慢性心不全患者の治療のための肺動脈に埋め込む血圧センサの治験を2019年に、FDAから条件付き治験装置免除の承認を得て開始した。埋込電子機器への給電は磁気共鳴型のワイヤレス給電で行う。周波数は13.56MHz帯で通信も行う。 米国を始め、中国、欧州や韓国などで埋込センサの研究開発は盛んに行われている。周波数は異なるものの、コイルを用いたワイヤレス給電がよく使われている。なお、可聴音や超音波を用いたワイヤレス給電の例もある。
4. 最後に
環境発電については、IoTで期待されるものの決定打がないのが現状である。既存の材料やデバイスを応用するだけでなく、材料開発からじっくり取組むことがこの状況をブレークすることに繋がるのではないかと考えられる。また、マイクロ波給電が救世主となるかもしれないが、ヒトとの共存など多くの課題を抱えている。
株式会社英知継承では、本テーマに関して当該専門家による技術コンサルティング(技術支援・技術調査)が可能です。下記よりお気軽にお問い合わせください。
▼「電気電子・光通信」に関連する技術解説一覧
Co-Packaged Optics(CPO)とフォトニック集積回路(PIC)
テラヘルツ波の光ファイバ無線技術(テラヘルツ・オーバー・ファイバ)
直流給電(DC給電)はZEHを加速するか? 住宅DC化の最新動向と課題
量子センサとは何か ― 原理・種類・応用から実用化動向まで ―
DRAMとSSDのギャップを埋める高速不揮発性メモリの最新動向
自動運転を支える車載E/Eアーキテクチャと車載ネットワークの最新動向